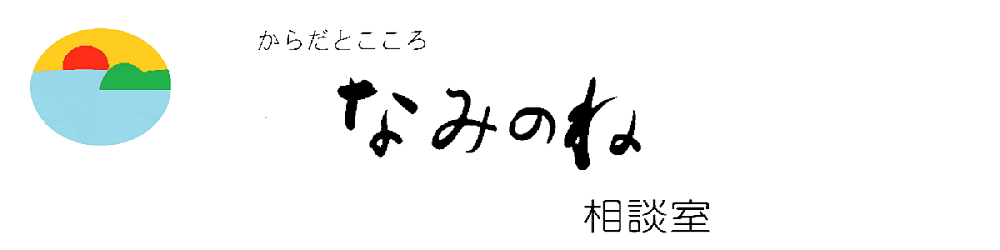小説なみのね
「小説なみのね」とは
NEW
「新・小説なみのね」
「小説なみのね」は、クライエントとの対話。
「新・小説なみのね」は荒唐無稽な話として始めました。
これまでの「小説なみのね」
主として臨床動作法という器の中で、一人の人と向き合っていると、その瞬間・瞬間に火花が散り、さまざまなことが起こってきます。
それらは大切な、その人の人生そのものであり、決して他者に開示すべきではない情報です。
ですから、そのままを語ることは許されませんし、そもそもそんなことはできるものではありませんが、
そのエッセンス的なこと、上澄み液のようなものを示すことはできないかと考えたときに、短い小説にしてみようかと思い立ちました。
小説ですから、もちろん作り話です。
私の勝手な思いこみや解釈でつづったものです。
ですから、そのようなものとして読んでいただければ幸いです。
2025年5月29日からは、「新・小説なみのね」を開始しました。
「小説なみのね」
NEW
新小説なみのね第21話影の衣と学徒の灯」新小説なみのね第20話「新しき箒と、わすれものの王」
新小説なみのね第19話「雪の学院を去る律の巫女」
新小説なみのね第18話「太守の退きし日」
新小説なみのね第17話「浄めの風の神話」
新小説なみのね第16話「水を天に放つもの」
新小説なみのね第15話「光る冠の若者」
新小説なみのね第14話「大海の二つの船」
新小説なみのね第13話「ニラを植える守り人」
新小説なみのね第12話「苔の小瓶の神話」
新小説なみのね第11話「十日堂の封じ水」
新小説なみのね第10話「川の向こうのパン屋」 新小説なみのね第9話「境界を守る夜の戦い」 新小説なみのね第8話「卵を忘れかけた電車の中で」 新小説なみのね第7話「風の教室」 新小説なみのね第6話「青信号と雪の朝に」 新小説なみのね第5話「グラウンドの扉」 新小説なみのね第4話 「赤い背中」 新小説なみのね第3話 「ぶっきらぼうな彼女」 新小説なみのね第2話 「湖のまなざし」 新小説なみのね第1話 「透明な水の大学にて」 小説なみのね第12話 ひまわりちゃん 小説なみのね第11話 複雑系から単純系へ 小説なみのね第10話 髪 小説なみのね第9話 りんご 小説なみのね第8話 二階ぐらし 小説なみのね第7話 水のような関係2 小説なみのね第6話 水のような関係 小説なみのね第5話 かすみちゃん 小説なみのね第4話 俺のきらいなもの 小説なみのね第3話 レイ 小説なみのね第2話 くぐりぬけて 小説なみのね第1話 喫茶「なみのね」相談室